 団体戦である。
団体戦である。
前田日明のリングス引退後、まず打ち出された企画は、3対3の勝ち抜き対抗戦という新たな試合形式だった。柔道、剣道などでは既にお馴染みのやり方ではあるが、勿論、総合格闘技では始めて。プロの格闘競技ということで見ても、プロレスで何回か「軍団抗争」として行われた以外はほとんど例がない。
 リングスは、何を目指して、団体戦というルールを実施したのか。
リングスは、何を目指して、団体戦というルールを実施したのか。
まず具体的な試合結果からその効果を見てみよう。本大会で行われた団体戦は二つ。ロシアAチーム(先鋒スーセロフ、中堅ミーシャ、大将ハン)対オランダチーム(先鋒ナイマン、中堅フライ、大将カステル)と、ジャパンBチーム(先鋒坂田、中堅山本宜久、大将金原)対ブルガリアチーム(先鋒トドロフ、中堅ジュリアスコフ、大将ペトコフ)である。個別には、二人抜きがなかったため、併せて9試合が行われた。
結果、9試合とも、10分という普段の試合の半分の制限時間にも関わらず、全て時間内に決着がついた。特にロシアA対オランダについては、5試合全てが決着タイム2分台という短期戦。いささか古びた言い回しを使わせてもらうならば、秒殺の嵐ということになった。オランダチームの勝利、ブルガリアチームの善戦という意外な展開も含め、この新たなルールは、予想以上の面白さをもたらしてくれたということができるだろう。
 1D=1E、2ロストポイントで試合が終わってしまうこと。加えて、勝ち抜き戦であるため、無駄に体力を消耗したくないという意識が働き、ポイントを守り抜くのではなく、ともかく「後1ポイントを取って」試合を終わらせてしまいたくなること。こういったルールの妙が、各試合を、非常に攻撃的なものとした。相手の動きをじっくりと観察する。前半、ディフェンシブに動いて、スタミナを消耗させ、隙を作る。普段使われているこうした戦略は捨て去られ、果敢な打撃ラッシュ、掴まえたら速攻で関節を極めにかかるというアグレッシブな動きに終始したのである。
1D=1E、2ロストポイントで試合が終わってしまうこと。加えて、勝ち抜き戦であるため、無駄に体力を消耗したくないという意識が働き、ポイントを守り抜くのではなく、ともかく「後1ポイントを取って」試合を終わらせてしまいたくなること。こういったルールの妙が、各試合を、非常に攻撃的なものとした。相手の動きをじっくりと観察する。前半、ディフェンシブに動いて、スタミナを消耗させ、隙を作る。普段使われているこうした戦略は捨て去られ、果敢な打撃ラッシュ、掴まえたら速攻で関節を極めにかかるというアグレッシブな動きに終始したのである。
近代スポーツの歴史をひもとくと、常に攻撃させ続け、展開の激しい試合にするべくルールが改善されてきたことがわかる。オリンピック・レスリングは、試合時間を次々と短かくし、ポイント制を明確にすることによって、非常にスピーディな試合展開を実現した(世紀初頭までは相手のスタミナ切れを狙ってジャーマンのような大技を仕掛けるという大味な試合が多かった)。柔道では、消極的な姿勢は、指導の対象となる。格闘競技以外でも、サッカーにおけるオフサイドの制限の緩和など、同様のルール改定の例は多い。
リングスの団体戦ルールも、こうした大きな流れに沿ったものとして解釈することができる。
 スポーツ、あるいは、ゲームとして考えた場合、こういったルール改正は、明らかに望ましいものだ。加えてチームであるということ、つまり、「目に見える仲間がいる」ということも、スポーツ的なドラマ・感動を生み出す装置として、優れたやり方であるということができよう。 スポーツ、あるいは、ゲームとして考えた場合、こういったルール改正は、明らかに望ましいものだ。加えてチームであるということ、つまり、「目に見える仲間がいる」ということも、スポーツ的なドラマ・感動を生み出す装置として、優れたやり方であるということができよう。
だが、格闘技として考えた場合はどうか。
かつて船木は、近藤との試合に敗れた時、最初のエスケープを自分が取っていたことを理由に「格闘技的には勝利」と言ったことがある。また、前田は、昔、「格闘技は一人で闘うもの」なのだから、ラウンド間にセコンドの助力が得られるのは本来おかしいと発言していた。
一つのポイントも取られるべきではない。
一人の助けも得られるべきではない。
これが格闘技なのだとするならば、ディフェンスを二の次にしたポイント争いや、チームとしての闘いは、まさに邪道に他ならないことになる。
 誤解のないように言っておくが、格闘技の根源に「一対一の素手での殺し合い」があったという歴史的事実は全くない。真面目な殺し合いというものは、本来、武器を使って集団でやるものである。徒手格闘技の試合に「真剣」勝負、殺し合いの幻影を求めるのは、あくまでファンタジー。つまり、選手サイド、あるいは観客サイドの心持ちの問題でしかない。 誤解のないように言っておくが、格闘技の根源に「一対一の素手での殺し合い」があったという歴史的事実は全くない。真面目な殺し合いというものは、本来、武器を使って集団でやるものである。徒手格闘技の試合に「真剣」勝負、殺し合いの幻影を求めるのは、あくまでファンタジー。つまり、選手サイド、あるいは観客サイドの心持ちの問題でしかない。
こうしたこと、競技としての格闘技の方向性にあるべき真実など存在していない、ということを踏まえていうなら、リングスが、団体戦というものを通じて、よりゲーム性を高め、近代スポーツとしての進化を図っていくのは、おそらく「正解」であろう。なぜなら、先に述べた「格闘技性」ということでは、バーリ・トゥードというライバルが既に存在しているからだ。
 グラウンド・パンチという究極の一撃を巡って展開されるバーリ・トゥードの試合は、まさに、格闘技そのものである。相手の体を地面に押さえつけ、その体勢から、顔面に、がつんがつんという音を立てて鉄拳を思いきり落としていく。
グラウンド・パンチという究極の一撃を巡って展開されるバーリ・トゥードの試合は、まさに、格闘技そのものである。相手の体を地面に押さえつけ、その体勢から、顔面に、がつんがつんという音を立てて鉄拳を思いきり落としていく。
ボクシングのラッシュ、キックの肘、そしてグラウンド・パンチ。
顔面を打突し、腫れ上がらせ、血飛沫を上げさせる。実際のダメージとは別に、これほど鮮やかに殺し合いの幻影を見せてくれるものはない。この期待、あるいは、それへの懼れが、バーリ・トゥードの試合に、類希な緊張感をもたらす。それは、激しいとはいっても、所詮は「点の取り合い」に過ぎないスポーツの興奮とは一線を画すものである。
 総合格闘技の世界で、バーリが格闘技性で売っていくのならば、リングスはスポーツとしての道を歩むべきだろう。華麗な関節技。空手流、ムエタイ流、マーシャル・アーツ流の様々な蹴り。リングスがアピールすべきは、こうした、各種の技術であり、それを駆使してさわやかに闘い抜く各国のアスリート達のドラマである。 総合格闘技の世界で、バーリが格闘技性で売っていくのならば、リングスはスポーツとしての道を歩むべきだろう。華麗な関節技。空手流、ムエタイ流、マーシャル・アーツ流の様々な蹴り。リングスがアピールすべきは、こうした、各種の技術であり、それを駆使してさわやかに闘い抜く各国のアスリート達のドラマである。
そうであるならば、今回の団体戦ルールの採用は正しい。
前田という、格闘技性を一身にまとったカリスマが退場した今、リングスの進むべき道は、まさにここにあると言っていいのではないだろうか。

↑全試合結果に戻る
| 





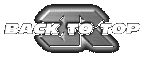
 スポーツ、あるいは、ゲームとして考えた場合、こういったルール改正は、明らかに望ましいものだ。加えてチームであるということ、つまり、「目に見える仲間がいる」ということも、スポーツ的なドラマ・感動を生み出す装置として、優れたやり方であるということができよう。
スポーツ、あるいは、ゲームとして考えた場合、こういったルール改正は、明らかに望ましいものだ。加えてチームであるということ、つまり、「目に見える仲間がいる」ということも、スポーツ的なドラマ・感動を生み出す装置として、優れたやり方であるということができよう。 誤解のないように言っておくが、格闘技の根源に「一対一の素手での殺し合い」があったという歴史的事実は全くない。真面目な殺し合いというものは、本来、武器を使って集団でやるものである。徒手格闘技の試合に「真剣」勝負、殺し合いの幻影を求めるのは、あくまでファンタジー。つまり、選手サイド、あるいは観客サイドの心持ちの問題でしかない。
誤解のないように言っておくが、格闘技の根源に「一対一の素手での殺し合い」があったという歴史的事実は全くない。真面目な殺し合いというものは、本来、武器を使って集団でやるものである。徒手格闘技の試合に「真剣」勝負、殺し合いの幻影を求めるのは、あくまでファンタジー。つまり、選手サイド、あるいは観客サイドの心持ちの問題でしかない。 総合格闘技の世界で、バーリが格闘技性で売っていくのならば、リングスはスポーツとしての道を歩むべきだろう。華麗な関節技。空手流、ムエタイ流、マーシャル・アーツ流の様々な蹴り。リングスがアピールすべきは、こうした、各種の技術であり、それを駆使してさわやかに闘い抜く各国のアスリート達のドラマである。
総合格闘技の世界で、バーリが格闘技性で売っていくのならば、リングスはスポーツとしての道を歩むべきだろう。華麗な関節技。空手流、ムエタイ流、マーシャル・アーツ流の様々な蹴り。リングスがアピールすべきは、こうした、各種の技術であり、それを駆使してさわやかに闘い抜く各国のアスリート達のドラマである。